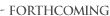|
Landscape Reimagined -風景のみかた-2026.1.10 - 2.21冬季休廊: |
| ©Pin-Ling Huang |
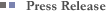
会場:nca | nichido contemporary art
会期:2026年1月10日(土)~ 2月21日(土)営業時間:火 – 土 11:00 – 19:00 (日・月・祝日休廊)
オープニングレセプション:1月10日(土)17:00 ~ 19:00
作家:今西真也 / リム・ソクチャンリナ / ピンリン・ホワン / ジャナイナ・チェッペ / ジーホン・リュウ / ヴィック・ムニーズ
安井曾太郎 / 里見勝蔵 *協力:日動画廊
nca | nichido contemporary art は新春第1回目の展覧会として、グループ展Landscape Reimagined -風景のみかた-を開催いたします。本展は上記、日動画廊及びncaが取り扱う近代および現代作家の風景画にフォーカスしています。彼らは各々のテーマ、制作活動を通して、様々な視点から風景画を探求し、表現してきました。過去を振り返り、それが後世にどのような道筋を築いてきたかを考察することで、風景画とういうジャンルがどれほど広く、進化してきたかを検証します。
自然景観や光の調和、事物の観察だけではなく、抽象的で感情的な表現によるパーソナルな内面世界、日常の断片の記録、現代社会が直面する課題の提示、観る者の視点に挑戦する過去の教訓の追跡、自然要素を通した人間関係の観察…。上記作家は、それぞれ独自の表現言語で風景という要素を芸術実践に取り込み、その物理的限界を超え、より深く、時に差し迫った問題に取り組むことに成功しています。人生、歴史、社会を語る風景。近代絵画と並列させることで過去を辿り、現在、未来を創造します。
ピンリン・ホワンの風景画は、スケッチブックに描き溜めた数多くのドローイングや習作をもとに、新たな世界に命を吹き込みます。流れる筆致と厚い層の下に浮かぶ空間構造を創り出すホワンのイメージは、具象と抽象の境界線を歩みながら、鑑賞者の立ち位置や視点に応じて新たな視覚的可能性を与えます。その表現言語の根幹をなすのは、作家の日常生活である。彼女はこれを個人的体験や旅の記憶と融合させ、想像上の新たな風景を生き生きと描き、時にそれは観る者に郷愁を誘います。
今西真也は東洋哲学、西洋の伝統絵画、そして日本美術を参照しながら、物質とイメージ、視点と距離の関係を探求し、我々の認識の曖昧さや不確実性を可視化しようと試みています。私たちの視点や姿勢のわずかな変化が新たな視覚的可能性を浮き彫りにし、私たち自身の存在と現実が、いかに有機的で予測不可能な変化に満ちているかを示します。
リム・ソクチャンリナは多様な芸術的実践を通じて、現代のカンボジアにおける政治や経済、環境、文化的変化やそれに伴う諸問題を探求します。巨大なグローバル資本と様々な政治的思惑によって急速に変化する社会や風景を記録し、これまでの地域のコミュティーや文化、自然が失われていく未来を問題視しています。
ジーホン・リュウは、文学、詩、哲学などからインスピレーションを得ながら、旅先で体験する出来事や風景が日常の偶然性と絡み合う、独特で表現豊かな表現を確立しています。地元の人々と交流を重ね、フィールドリサーチを通して言葉や絵画で表し難い、音や時間、温度、感情といった要素を異なる次元で枠組み化し、自然景観の単なる描写や世界の観察を超え、それらを可視化しようと試みます。
ヴィック・ムニーズはPictures of Earthシリーズをはじめ、これまでの制作で多く地球や自然、社会をテーマとした作品を多く手掛けてきました。美術史上の著名な画家よって描かれた有名なイメージや、既視感のある風景、時にコミカルなイメージを用い、チョコレートや砂糖、紙、パズル、糸、ゴミなどのさまざまな素材を使ってそれを巧みに再構築し、写真で表現します。親しみやすい素材とイメージを用いて日常に観ること、現実の認識を再定義し、我々に新たな視点、世界を与えます。ムニーズは過去と現在を横断し、急速に進化する世界を受け入れ、楽しみながらも未来へ起こりうる問題に警鐘を鳴らします。
ジャナイナ・チェッペは、絵画、写真、映像、彫刻等さまざまな芸術的実践を通じて、幻想と現実の境界線を行き来します。チェッペの抽象絵画は、水生生物、植物、人間といったあらゆる自然の要素を探求し、有機的で親密、かつ動的なフォルムは生命の進化と変容をも想起させます。彼女の作品は自身のブラジルのアトリエを取り巻く豊かな自然環境を強く反映しており、自然との個人的な関わりを通じて、人間と自然界の複雑な相互作用を模索しています。
日本の洋画壇の巨匠の1人である安井曾太郎(1888 – 1955)はフランスで学び、特にセザンヌに強い影響を受けます。対象を様々な視点で描くセザンヌの手法を取り入れながら独自の手法で日本の風土を捉えた風景画は、大胆な輪郭と繊細な色調で高く評価され、現代まで多くの画家たちに多大な影響を与えています。また、同時代に活躍した里見勝蔵(1895 – 1981)も安井に傾倒した画家の1人です。里見は渡仏するとブラマンクに師事し、フォーヴィズムの影響を受けた、力強く鮮やかな色彩に加え、感情や当時の体温をも感じる、独自の表現を確立しました。